「多様性」という言葉を、日常のあちこちで耳にします。
そして、まるでそれが“現代の正しさ”の象徴であるかのように扱われているように感じます。
もちろん、多様性を尊重すること自体はとても大切なことです。
けれど、いつの間にか「多様性を認めること」そのものが義務のようになり、人々の心に、静かな圧力のようなものが生まれているようにも思います。
違いを認め合うはずの言葉が、いつしか“正しさの型”として人を縛ってはいないか。
そんな矛盾について、「敬意」という視点から、多様性との共存について考えてみたいと思います。
多様性が“正しさ”になる危うさ
本来、多様性とは「違いを尊重する」という柔らかな考え方のはずです。
それぞれが異なる背景や価値観を持ち、それを受け入れ合うことで社会が豊かになる——
その理念には、誰もが共感できる温かさがあります。
しかし最近では、その“尊重”がいつの間にか“同意”と混同されているように感じます。
異なる考え方に対して「理解できない」と言うだけで、非寛容だとか、差別的だといった評価を受けることがあります。
本来の多様性は、同意を求めるものではなく、「そう考える人もいる」と静かに受け止める力のことだと考えています。
それなのに、いつしか“正しさの基準”が生まれ、そこから外れることが、まるで誤りであるかのように扱われてしまう。
多様性という言葉が持つ本来の自由さが、“正しさ”という枠組みによって少しずつ形を変えられてしまう。
そこに、私たちが見落としがちな危うさが潜んでいるのだと思います。
敬意とは、相手を変えずに認める力
「敬意」という言葉には、どこか古風で形式的な響きがあります。
けれど、本来の敬意とは、相手を持ち上げたり、無理に理解したりすることではなく、“相手を変えようとしないまま、存在を認めること”ではないでしょうか。
たとえば、意見の違う相手に対して、「自分とは違う考え方だ」と分かったうえで、その人の選択や背景を尊重する。
その距離感の中にこそ、敬意は宿るのだと思います。
敬意には、相手を自分の枠に収めようとしない余白があります。
その余白があるからこそ、互いの考えが交わらなくても共にいられる。
それは、理解よりも深い形の受け入れのように思います。
多様性を語るうえで大切なのは、相手を“同じ側”に引き寄せることではなく、“違うまま共にある”という関係を築けるかどうか。
敬意は、そのための静かな支えになるのだと思います。
敬意による共存
多様な価値観が共存する社会で、本当に求められているのは、すべてを理解し合うことではなく、理解できないままでも認め合える関係だと思います。
その“認める”という感覚こそが、敬意の原点なのかもしれません。
相手の立場や選択に踏み込みすぎず、それでも否定しない。
その姿勢があってはじめて、違いが豊かさや視野の広さへとつながっていきます。
そして、それは社会に対してだけでなく、自分自身の選択にも向けられるものだと思います。
セミリタイアやFIREのような生き方は、まだまだ少数派ですし、おそらくこれからも、少数派のままであり続けるでしょう。
けれど、様々な価値観を認めるという感覚こそが、そうした“マイノリティな選択”を受け入れる社会の土台になえるのだと思います。
だからこそ、私は“敬意”という言葉を大切にしていきたいと思います。
相手を、そして自分をも、変えずに認める力として。
そして、自らの選択を自ら否定するという矛盾を生じさせないために。
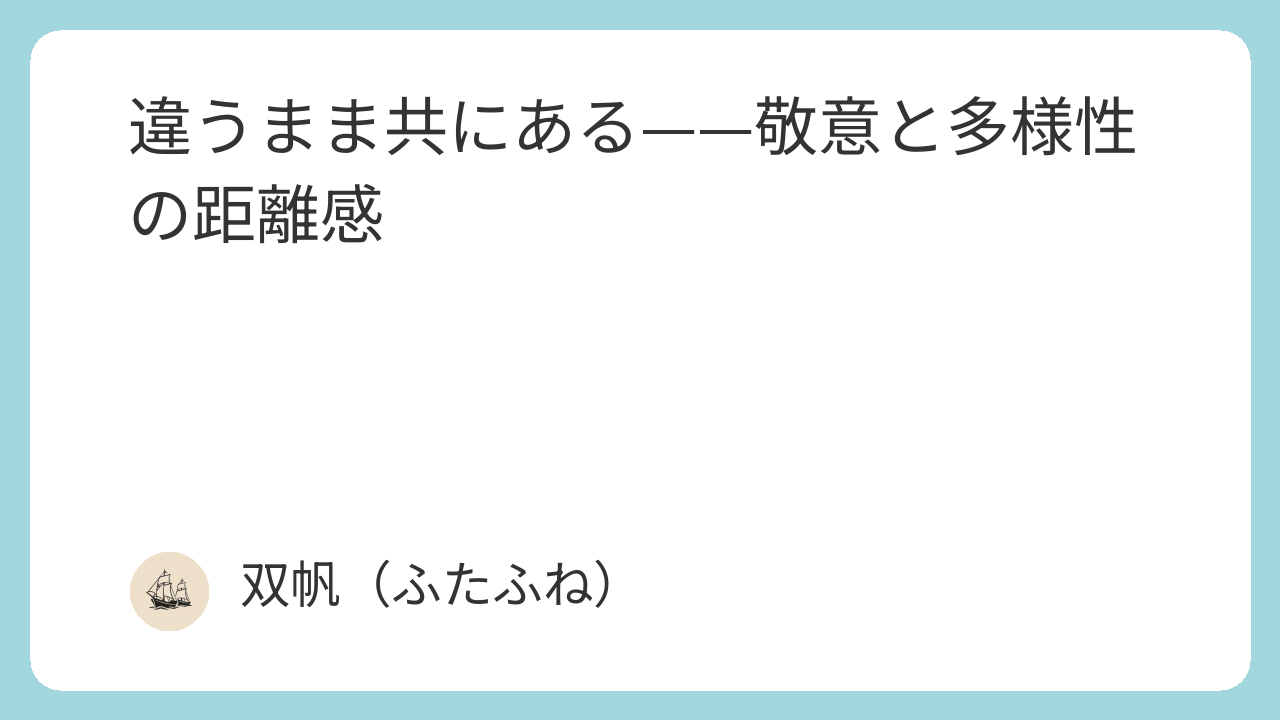
コメント